ここから本文です。
[伝統文化]あめあめふれふれ、さぬきの雨乞い行事

 伝統文化
伝統文化
香川用水が本格通水した1975年(昭和50年)頃まで、香川県の農業用水などは、日照りによる水不足に悩まされていました。
特に戦前までは各地でさまざまな雨乞い行事が行われていたそうです。

![]() 籠もって、もらって、怒らせて、踊る
籠もって、もらって、怒らせて、踊る
雨乞いの方法は大きく五つに分かれます。一つは「籠(こ)もる」。氏神さまや竜王さまに籠もって雨を祈願します。讃岐の国司であった菅原道真は、城山神社に籠もって断食し、雨乞いをしたと伝えられています。「もらい水」というのは、降雨に御利益があるという社寺や淵の水をもらい、神前に供えたり、淵や池に入れて雨乞いをする方法です。水の代わりに、こんぴらさんなどから火種をもらって、たき火をたくこともありました。
水神や竜神がすむという場所に不浄物を投げ捨てるという「竜神を怒らす」方法もありました。有名な「雨乞踊」は、鐘を打ち、太鼓を鳴らし、踊ることで雨が降るのを願います。

城山神社/坂出市の城山の東麓に鎮座する「城山神社」。境内には菅原道真を祭る「雨請天満宮」があります。

甕塚/高松市由良町の清水神社の「甕塚」には、甕を使う雨乞い行事が伝えられています。
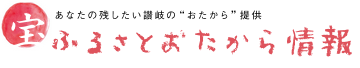
「和田雨乞踊(観音寺市豊浜町)・田野々雨乞踊(観音寺市大野原町)」
観音寺市に伝わる二つの雨乞い踊りは共に香川県指定無形民俗文化財。豊浜町和田に伝わる「和田雨乞踊」は、約400年前に薩摩法師が歌と踊りを伝え「雨乞」をしたことに始まるといわれています。大野原町五郷、田野々地区に残されている「田野々雨乞踊」も400年前の慶長の頃、薩摩法師が伝えたという踊り。「けいご」と呼ばれる歌い手を中心に、ゆかたに白だすき、手甲(てっこう)、脚絆(きゃはん)姿に締め太鼓をかけた太鼓打ち、花笠をつけた子ども、編み笠の大人たちが輪になり、歌に合わせて踊る素朴な踊りです。

和田雨乞踊
![]() 国・県指定文化財の雨乞踊
国・県指定文化財の雨乞踊
| 区分 | 名称 | 所在地 | 所有者 (管理団体) |
開催日・場所 |
|---|---|---|---|---|
| 重要無形民俗文化財 | 綾子踊 | 仲多度郡まんのう町佐文 | 佐文綾子踊保存会 | 隔年の8月末から9月の日曜日 加茂神社 |
| 重要無形民俗文化財 | 滝宮の念仏踊 | 綾歌郡綾川町 | 滝宮念仏踊保存会 | 8月25日 滝宮天満宮 |
| 県指定無形民俗文化財 | 北条念仏踊 | 坂出市大屋富町 | 北条念仏踊保存会 | 不定期 |
| 県指定無形民俗文化財 | 南鴨念仏踊 | 仲多度郡多度津町南鴨 | 南鴨念仏踊保存会 | 不定期 |
| 県指定無形民俗文化財 | 和田雨乞踊 | 観音寺市豊浜町和田 | 和田雨乞踊保存会 | 7月末の土曜日 |
| 県指定無形民俗文化財 | 田野々雨乞踊 | 観音寺市大野原町田野々 | 五郷田野々雨乞踊保存会 | 不定期 |
| 県指定無形民俗文化財 | 坂本念仏踊 | 丸亀市飯山町川原 | 坂本念仏踊保存会 | 3年に一度8月25日 滝宮天満宮で特別奉納 |
| 県指定無形民俗文化財 | 大川念仏踊 | 仲多度郡まんのう町中通 | 大川念仏踊保存会 | 旧暦の6月14日に近い日曜日 大川神社などで奉納 |
さぬきのおたから総力取材
綾子踊(国指定重要無形民俗文化財)
昔から干ばつなどの水不足に悩まされてきた香川県には、民俗芸能として「雨乞い踊り」が伝承されてきました。そのなかの一つ「綾子踊」は、現在のまんのう町(旧仲南町佐文)に伝わる踊りです。伝えによると、その起こりは、干ばつに悩まされる村の様子を綾という女性が旅の僧に話したことから始まります。僧は、龍王に願いをこめて雨乞い踊りをすれば雨が降ると教え、村人とともに綾夫婦の鉦鼓や太鼓の音に合わせて踊ったところ、一瞬にして滝のような雨が降ったといわれています。それ以来、水不足の時期に綾が踊ってみると雨が降ったことから、この雨乞い踊りは、誰ともなく「綾子踊」と呼ばれるようになりました。「綾子踊」は、女性が舞うのではなく男性が女装して舞います。現在は、2年に1度、まんのう町の加茂神社に奉納されています。

綾子踊/まんのう町
このページに関するお問い合わせ