ここから本文です。
HIV感染者、ハンセン病回復者の人権
HIV感染者の人権
正しい知識を持ちましょう。
 現在、日本では、1日に約4人の方がHIVに感染しており、全国的な広がりを見せています。エイズは、HIVというウイルスに感染することによって引き起こされる病気で、治療しなければ数年の潜伏期間を経て発病します。
現在、日本では、1日に約4人の方がHIVに感染しており、全国的な広がりを見せています。エイズは、HIVというウイルスに感染することによって引き起こされる病気で、治療しなければ数年の潜伏期間を経て発病します。
この潜伏期間の間は、感染しても症状は出ませんが、他の人に感染させる力はあります。現在は、治療の進歩により、早期に治療すればエイズの発病を防いだり遅らせたりすることができ、発症しても治療で免疫力を高めることもできます。何より早期発見が大切です。
HIVの感染経路には、性行為・血液感染・母子感染の3つの経路がありますが、HIVはとても弱いウイルスで、人間の体以外では生きられません。日常生活のなかで、性行為を除けば、接触による感染や空気感染の心配はありません。
したがって、誰もが感染する機会があり、本人が気づかないうちに大切な人にうつしてしまうこともあります。逆をいえば、予防しさえすれば防げる病気なのです。
エイズを防ぐということは、ウイルスを体に入れないことです。そのためには、コンドームが最も効果的な防御方法です。性的接触、つまりセックスの際に必ずコンドームを正しく使用して感染防止を心がけていただきたいと思います。
あなたやあなたの友人がHIVに感染したら…
正しい知識を持って接しましょう。
HIVに感染しても、最近は治療薬の開発により、エイズの発症を防いだり、遅らせたりすることが可能であり、何年も健康な生活ができます。また、エイズを発症しても治療で免疫力を高めることもできます。
同じ職場、学校で生活していても感染することはありません。身近な人などが感染していても、プライバシーを守り、今までと変わらない態度で接することが大切です。
しかし、HIV感染者に対しては今なお誤った知識を持っている人が多く、偏見や差別が解消されていないのが実態です。これまでにも、HIVに感染していることを理由に解雇されたり、医療機関で診察を拒否されたりするなどの人権侵害が起こっています。こうした人権侵害をなくすためにも、一人ひとりが正しい知識を持つことが必要です。
レッドリボン運動に参加しませんか
 赤いリボンを服や持ち物につけるレッドリボン運動は「HIV/エイズヘの理解」の印として世界的に広がっています。レッドリボンは、エイズに対して偏見を持っていない、エイズとともに生きる人々を差別しないというメッセージです。声高に理解を口にしたり、呼びかけるのではなく、無言のメッセージを送ってみませんか。あなたの赤いリボンが感染している人の目に留まれば、どれだけその人が励まされることでしょう。
赤いリボンを服や持ち物につけるレッドリボン運動は「HIV/エイズヘの理解」の印として世界的に広がっています。レッドリボンは、エイズに対して偏見を持っていない、エイズとともに生きる人々を差別しないというメッセージです。声高に理解を口にしたり、呼びかけるのではなく、無言のメッセージを送ってみませんか。あなたの赤いリボンが感染している人の目に留まれば、どれだけその人が励まされることでしょう。
香川県の取り組み
保健所において無料・匿名でHIV検査を受けられます。
希望される方は、最寄りの保健所まで相談してみてください。
世界エイズデー(12月1日)やHIV検査普及週間(6月1日〜7日)にあわせて、臨時のHIV検査を実施したり、エイズに対する正しい知識を周知しています。
県内のエイズ相談はこちらまで
- 東讃保健福祉事務所
0879−29−8261 - 小豆総合事務所
0879−62−1373 - 中讃保健福祉事務所
0877−24−9962 - 西讃保健福祉事務所
0875−25−2052 - 高松市保健所
087−839−2870
※エイズテレホン案内(自動音声)
087−863−0110
ハンセン病回復者の人権
正しく理解しましょう。
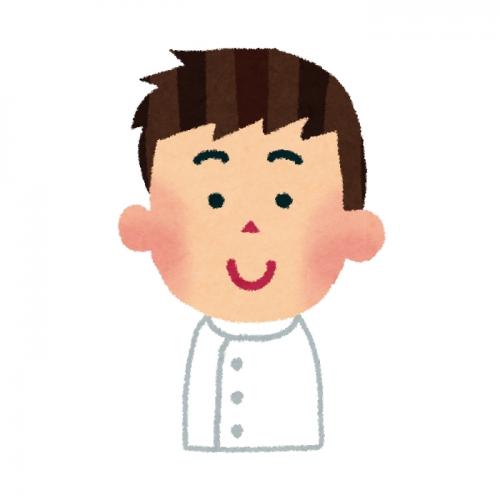 ハンセン病は有史以来存在する病気ですが、かつては、原因がわからないため、不治の病や遺伝する病気と考えられたり、外見上の変形があるため、恐ろしい病気と思われてきました。
ハンセン病は有史以来存在する病気ですが、かつては、原因がわからないため、不治の病や遺伝する病気と考えられたり、外見上の変形があるため、恐ろしい病気と思われてきました。
1873(明治6)年、ノルウェーのハンセン博士によって、らい菌による感染症であることが発見され、その後の研究により、治療法が確立し、治癒する病気になりました。
しかし、わが国では、治療法が確立した1960(昭和35)年頃以降も隔離政策がとり続けられ、1996(平成8)年の「らい予防法」廃止まで続きました。この隔離政策によって、社会にハンセン病は伝染性の強い病気であるとの過度の認識が広まり、偏見が助長され、入所者やその家族の方々は様々な差別を受けてきました。
2001(平成13)年5月、ハンセン病の患者・回復者に対する国家損害賠償責任を認めた熊本地裁判決により、ハンセン病問題は大きな第一歩を踏み出しました。
しかし、患者・回復者の尊厳が完全に回復したわけではないので、ハンセン病問題の解決の促進に関しての基本理念を定めた「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が2008(平成20)年6月に成立しました。
ハンセン病はどういう病気でしょうか?
- 感染力の極めて弱い「らい菌」によって引きおこされる感染症で、遺伝する病気ではありません。
- ハンセン病は、皮膚や末梢神経の病気で、外見上に特徴的な変形が生じたり、あつさ、つめたさ、痛みなどの感覚が麻庫するため、火傷や傷ができてもわからなかったりすることがあります。そのため、変形や機能障害という後遺症が残ることがあります。
- らい菌の感染力は極めて弱いので、抵抗力の極めて弱い状態で、生菌に繰り返し接触しなければ感染することはありません。抵抗力が弱い乳幼児でも、栄養状態がよく、衛生環境が良い場合は、ほとんど感染しません。しかも、感染してもほとんど発病の可能性はありません。また、療養所の入所者等、軽快した人と接触しても感染することはありません。
- 1943(昭和18)年、特効薬プロミンの有効性が報告され、現在では、医学の進歩により、リファンピシン・ジアフェニルスルホン(プロミンの改良薬)・クロファジミンなどによる多剤併用療法で完全に治る病気になりました。早期発見・早期治療すれば、後遺症の心配もありません。
香川県の取り組み
ハンセン病問題の早期解決に向けて、香川県では次のような事業を行っています。
普及啓発事業
ハンセン病に対する正しい知識の普及啓発を行い、県民の偏見や差別を解消するため、パンフレットの配布やホームページによる広報や入所者作品展・啓発展の実施及び入所者と県民の交流会等による啓発事業を実施しています。
福利厚生事業
入所者の気持ちに配慮しながら、社会復帰を支援するため、次のような事業を行っています。
訪問事業、郷土名産品等の送付、里帰り事業、療養所退所者に対する医療・介護費の助成など
過去の検証調査事業
過去のハンセン病施策の実態を把握するため、「大島青松園」の入所者等に対する聞き取り調査を行い、回顧録『島に生きて?ハンセン病療養所入所者が語る』にまとめました。この記録は、今後、啓発に活かしてまいります。
心のバリアフリーを!
今後は、ハンセン病の患者・回復者の方々も、自由にそして安心して生活ができるように、偏見をなくしていかなければなりません。
私たちは、私たちの社会が患者・回復者の方々に苦痛を与えてきたことを、社会の一員として深く心に刻み、偏見や差別の解消に努めなければなりません。
社会に残る偏見と長い療養生活のなかで、社会復帰に消極的になりがちな入所者が、元患者であることを意識せず、ともに生きていけるよう、ハンセン病を正しく理解し、温かい心をもって、自然な交流ができるよう、努力しましょう。
このページに関するお問い合わせ